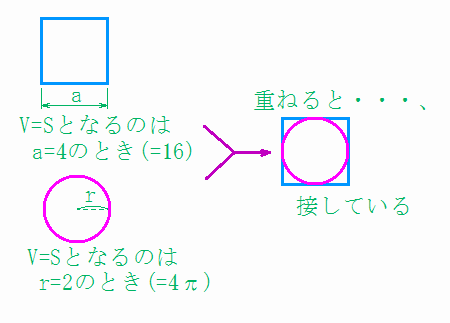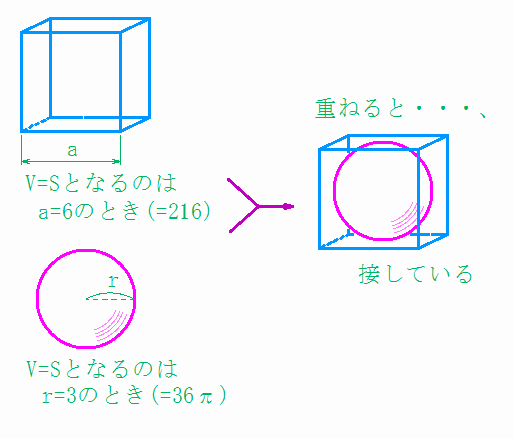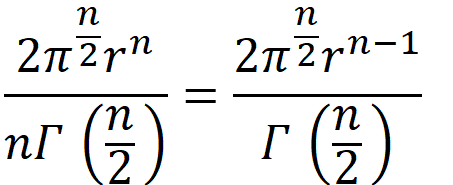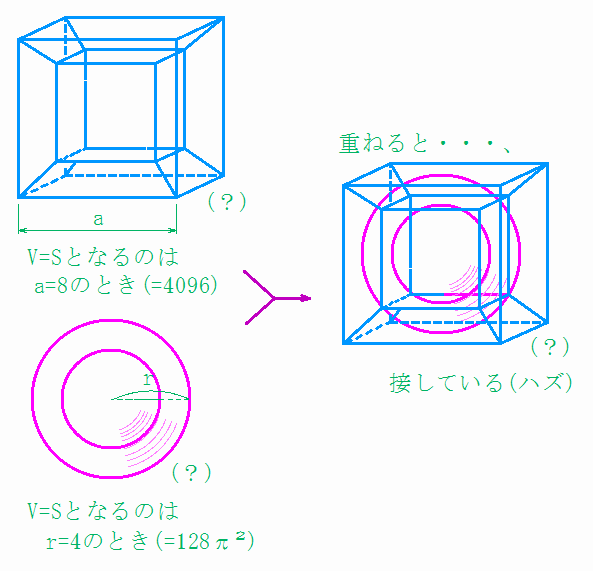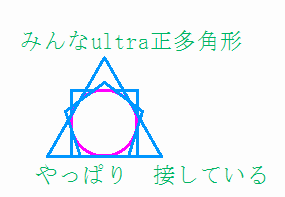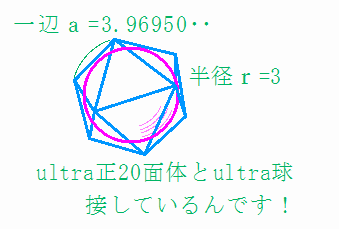≪1≫ いつの時代も万人を魅了しつづける円周率 πさん。愚生のふるいノートに、これの近似値についての書き込みがありましたので、本日はこれを今風にリメイクして書き留めておきたいと思います。当時はなにかべつのキッカケがあったかも?(数学雑誌で関連記事が載ってたーとか)ですが、手書きのノートには「平方根・立方根とかの数表をながめていて…」となっていました。此れ即ち観察数学。

≪2≫ π の近似値といえば、まずは 22/7 とか 355/113 が定番ですが、もひとつ √10 というのも有名。この √10 は、むかしむかし中国の張衡(ちょう こう)さんという方が言い出したんだとか。
近似のぐあいを表すのに、まえにも使いました「小数点以下何桁まで数値が一致しているか関数g(a) 」で表しますと、先ほどの近似ぐあいはつぎのような感じですね。(gとかは自家製記号です、念のため)
g(22/7) =g(3.14285・・・) =2
g(355/113) =g(3.14159 29203 ・・・) = 6
g(√10) =g(3.16227 ・・・) =1
「平方根なら僅か1ケタしか一致していないとおっしゃる。これはさみしい。それでは、立方根とかではどうなの?」と思うのは正しい考え。
そこで、カタカタっとやると (3)√31 (ちいさい (3) は、立方根の意味ですね) が出てきて、
g((3)√31) =g(3.14138 ・・・) = 3
となって、精度は3となり少々アップとなりますね。
≪3≫ さらにコトを進めるにあたり、n乗根で最良近似となる正整数をan としましょう。するってーと、上記の結果は、a2=10、a3=31 となります。また、a1=3 としておきます。
この数列{an }は、天下の数表OEISさんにはA002160でちゃんと登場されていまして、
3,10,31,97,306,961,・・・
とのことであります。これは、πのn乗に「最も近い」整数とのことですが、整数を採用する場合に切り捨てるのかあるいは切り上げるのかについては、ビミョウです。ここのところOEISさんにでは、床関数・天井関数としてA001672 (床(Pi^n))、A001673 (天井(Pi^n))もありますので3列にして観察してみます。きいろの着色部は、「最も近い」に採用されている側の候補であります。

実際にn乗根を計算し、π との差をみてみますと、

フロア側か天井側かは、上記の「最も近い整数」とは一致しているようですが、右にいったり左にいったりと規則性はナシと見受けます。π の性格からしてこれはずっと続く?
≪4≫ このほか、以下のことが観察されます。
・精度自体については、単調減少とはいえない。
実際のところ、n=4,6,12,16、…では悪化している。たとえば、
g((3)√31) =g(3.14138 ・・・) = 3
g((4)√97) =g(3.13828 ・・・) = 1 ・・・アッカ
・軽微な注意ですが、n=4のばあいの97のつぎの98では
g((4)√98) =g(3.146346 ・・・) = 2
となって桁数一致度関数gでは 98のほうがマシにみえますが、
|(3)√97-π|=0.0033 …
|(4)√98-π|=0.0047 …
となり、(3)√97のほうが最適な近似値といえます。
・あるnから先では単調減少かというと、πの超越性からして、たぶん、
そうではない?
・公比 an+1/an は、極限値 π に収束するようだ。これは
「鳩ノ巣原理」風論議で説明が着きそう。

an+1/an → π のようす
≪5≫ ふろくですが、今回の観察のとちゅうで次のようなものにも出会えました。
(=は ≒ のイミです...)
![]() (g=3)
(g=3)
![]() (g=4)
(g=4)
![]() (g=5)
(g=5)
以上のような数値観察の旅は費用もかからず、前期高齢者のボケ防止には最適なもののひとつではなかろうかと思ったりしております。
本日も、ご静読ありがとうございました。
参考
OEISさん、Wikiさん